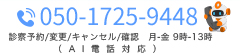広報からのご案内
From Public Relations
Medical Note掲載記事
(公開日:2025年4月24日)
医療インフラの偏在がもたらす課題
千葉県船橋市が直面する「ひっ迫した医療」の現状とは?
千葉県船橋市は緩やかながら人口が増えている
人口の減少に頭を悩ませている自治体が多い中、当院がある千葉県船橋市は人口増加が続いている全国でも数少ない地域です。その意味では発展が期待できる魅力的な街と言えるのかもしれません。しかし、地域医療の面から見ると人口当たりの医療資源が不足しており、医療インフラがぜい弱なことが課題になっています。
人口10万人あたりの医療インフラは全国平均を下回る
船橋市の状況を、私が以前赴任していた鹿児島市と比較してみたいと思います。鹿児島市は人口が約58万人(2025年2月)で、当院がある船橋市の約65万人(同)よりやや少ない都市です。しかしながら病院の数を比較すると、鹿児島市が80施設を超えるのに対し、船橋市は22施設しかありません。病床数も同様で、鹿児島市が1万2000床を超えるのに対して船橋市は約4500床しかなく、船橋市の病院数は鹿児島市の約4分の1、病床数は約3分の1という計算になります。また、人口10万人あたりに換算すると、病院数は鹿児島市が約14.3施設で船橋市が約3.4施設、病床数は鹿児島市が約2086床で船橋市が702床です。ちなみに全国平均(人口10万人あたり)は病院数が約6.4施設、病床数が約1164床です。日本でも病院が多い街である鹿児島市と比較するのは適切ではないかもしれませんが、船橋市は全国平均を大きく下回っており、医療インフラがぜい弱な地域だと言えるのではないでしょうか。
多い時には4人に1人が市外へ救急搬送される
病院数と病床数が不足すると、救急医療をはじめとした医療現場はかなりひっ迫します。それであるにもかかわらず、ここ最近の船橋市の救急出動件数は増加傾向にあり、直近では年間4万件を超えています。そのため、船橋市内の病院で全てを受け入れることが難しく、市外の病院に搬送されるケースが増えてしまいました。その割合は20%~25%に達することもあり、救急医療を担う身として忸怩(じくじ)たる思いです。また、少し前にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流行したのはご存じかと思いますが、その際には船橋市の救急医療がひっ迫し、一部の患者さんが神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院に救急搬送されたこともありました。
二次・三次の垣根を超えて救急患者を診ている
救急医療に関してもう1つ付け加えると、人口約65万人の都市に、三次救急(生命に関わる重症患者に対応する救急医療)を担う病院が船橋市立医療センターしかないことも問題だと思っています。特に心筋梗塞のように、一刻を争う容態の患者さんの受け入れが滞る事態だけは避けなければなりません。そこで当院のような二次救急(入院や手術を要する重症患者への救急医療)を担っている中核病院が、三次救急がパンクしないよう、可能な限り患者さんを受け入れる努力をしているのが現状です。
市内で医療を完結できる体制を整えたい
医療がひっ迫すると、患者さんが路頭に迷いかねません。特に急性期の治療を終えたものの、自宅や施設に戻ることができない患者さんなどは、転院先が見つからずに在院期間が延びてしまう傾向があります。その結果、船橋市では多くの急性期の病院が満床に近い状態となり、さらに救急医療がひっ迫するという負のスパイラルに陥っています。
これらの課題を解決するためには、行政と消防、そして我々医療者が一体となって改善に取り組んでいかなければなりません。そのために必要なのは、地域の医療機関が連携し合い、限られた資源の中で最大限の力を発揮できる体制づくりだと考えています。
それと同時に、当院としても救急医療体制をより強化しつつ、予防医療、健康増進への取り組みにも注力して救急の患者さんを減らし、船橋市とその周辺にお住まいの方の健康寿命延伸に貢献したいと思っています。
船橋市は、今まさに医療のあり方が問われている街です。だからこそ、ここで育まれる医療の形が、他の都市にとっても1つのヒントになるかもしれません。誰もが安心して暮らし、もしもの時もすぐに頼れる——そんな地域を目指して、私たちはこれからも日々、地域の医療に向き合っていきます。